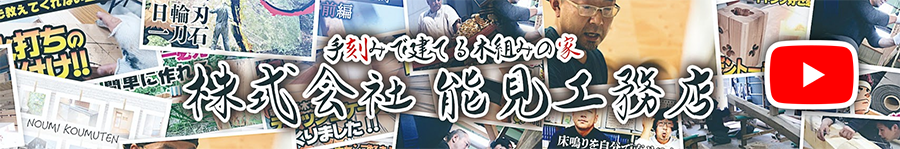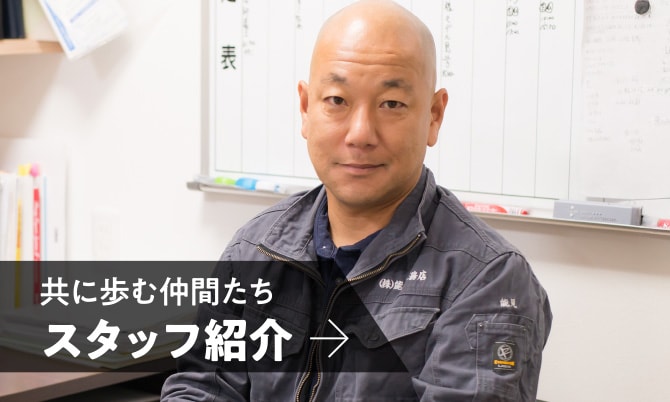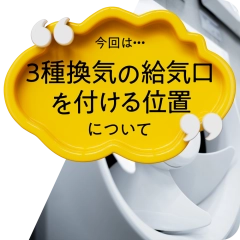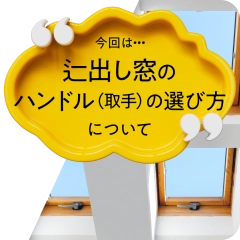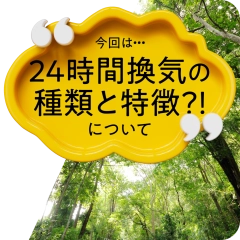ブログ
- 健康住宅・木の家[能見工務店]トップページ
- ブログ[一覧]
- ブログ[一覧]
- 2025年からの耐震基準
2025年からの耐震基準
2024年02月28日
こんにちは、京都の長岡京市で自然素材と高気密高断熱の家を建てている能見工務店の能見です。よろしくお願いします。情報過多の中、様々な情報が溢れかえっています。発信される情報というのは、なにかしら配信者の思惑が入って発信されます。

今日は、【2025年からの耐震基準】について書きたいと思います。
日本は本当に地震の多い国で2024年も能登の大地震から始まりました。
そもそも国は耐震基準を1950年に制定し、その基準は大地震の度に見直されてきました。
1950~81年に適用されていた「旧耐震基準」
1981~95年は「新耐震基準」
2000年~現在のものを「2000年基準」
とよんでいました。
旧耐震基準は震度5程度の中地震しか想定していませんでしたが、新耐震基準で震度6強程度の大地震にも耐えられるように改正されました。
新耐震基準をより強化したものが2000年基準で地耐力に合わせた基礎の設計、耐力壁の配置バランス等が求められるようになってきました。

現在、住宅の耐震性能を耐震等級の等級1から3で表します。
等級1は建築基準法における耐震基準を満たす強さ、等級2は等級1の1.25倍の強さ、等級3は等級1の1.5倍の強さとされています。
わかりやすく説明すると等級1はあくまで建物を建てる上での「最低限の基準」で、それを下回る強度の建築できないレベルです。
等級2は災害時の避難所に指定される学校や施設のレベルの強度。
等級3は救助活動や復興の拠点となる消防署や警察署のレベルの強度で、実は熊本地震で耐震等級3の木造住宅は倒壊していないのです。
では具体的に、どんな要素が住宅の耐震性能を左右するのか大きく4つに纏めました。
1つ目が耐力壁の量。
建物にかかる力を負担してくれる耐力壁が多いほど耐震性は高くなります。
2つ目がその耐力壁の配置バランス。
実は、熊本地震で壁量よりも壁や柱のバランスを表す指標の【直下率】が大事だということが分かったのです。安定性が欠けると建物全体の強さには繋がらないのです。
3つ目が床の耐震性能。
縦長の立体を想像すると分かりやすいのですが、中央あたりに支えがあるものとないものでは、力がかかった際の変形度合いが異なります。
そして4つ目が建物の重量。
軽いものより重いものの方が揺れやすいのです。
近年は住宅の高断熱化、太陽光搭載などの推進により建物の重量が増え、住宅が揺れやすくなっているといえます。
このことを踏まえ、国から求められる耐震性能は更に高くなりつつあり
2025年4月から、ZEH水準等の木造建築物の構造基準が変更となり、壁量計算や柱の小径が見直されるのです。
以上、自分はどの等級で建てたいと思いますか。
結論:許容応力度計算による構造計算をした耐震等級3の家に住むべし!!
2025年4月から一部の審査を省略できる4号特例がようやくなくなり構造計算をした家が必須になるので建てる人には安心です。“耐震等級3相当”ではなく“耐震等級3”の構造計算をして認定機関の審査を受けている家でなければ意味がないのです。
しっかり家を建てて貰う建築会社さんにアドバイスをもらいながら進めて後悔しない家づくりを実現して下さい。
この情報が皆様の役に立てば幸いです。

次回は
【土地を買う時に気を付けたいポイント】
について書きたいと思います。
長い文章を最後まで読んで頂きありがとうございました。
今年も残り306日。頑張っていきましょう。
YouTubeでも様々な情報を配信もしていますのでそちらも機会があればご覧ください。
能見工務店の自己紹介!
私たちの家づくりを支える「人」と「想い」をご紹介します。