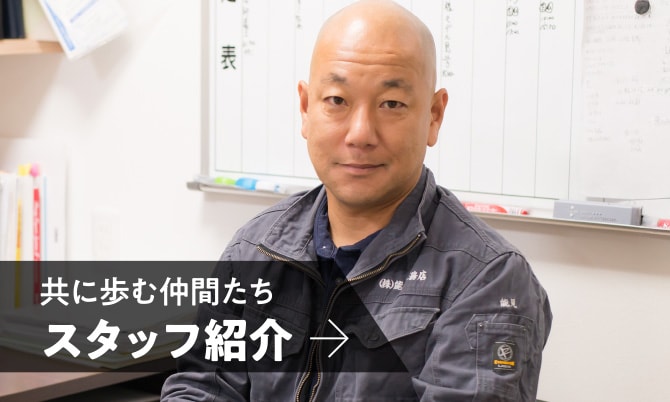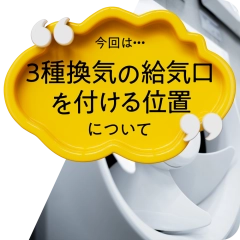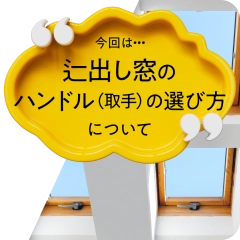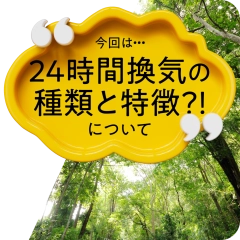ブログ
- 健康住宅・木の家[能見工務店]トップページ
- ブログ[一覧]
- ブログ[一覧]
- 自然乾燥の木と人工乾燥の木
自然乾燥の木と人工乾燥の木
2024年09月18日
こんにちは、京都の長岡京市で
自然素材と高気密高断熱の家を建てている
能見工務店の能見です。よろしくお願いします。
情報過多の中、様々な情報が溢れかえって
います。発信される情報というのは、
なにかしら配信者の思惑が入って発信されます。
まだまだ暑いですが、暦では9月で秋になり
ました。実は、秋から大体1月までが木を切る
最高に良い時期といわれています。木こりさんは
木を切ってからすぐに運ばず葉を付けたまま山で
乾燥させ(葉枯らし)雪が無くなって来る春先に
山から出してきました。それを材木屋さんが買い
大きめに製材してまた2~3年寝かして乾燥させ
使うサイズに再度加工して商品として売られて
来ました。昨今、流通が変わり材木屋さんが木を
乾かさなくなってきました。乾いた木が欲しい
私は材木屋さん迷子になりました。
今日は、
【自然乾燥の木と人工乾燥の木】
について書きたいと思います。
木は乾燥させて使う必要があります。出来る限り
含水率を下げてやる方が木の痩せや狂いは少なく
なり、家を建ててからの狂いが少なくなります。
木に含まれている水の比率を含水率という言い方
をします。含水率30%以下になると安定した
強度を発揮します。切りたての木には、水分が
たくさん含まれていて時間とともに水分が抜けて
だんだん乾燥していきます。水分が抜けていくと
木の大きさがひどい時は1cm以上も小さくなる
のです。これを“木が痩せる”と表現します。なぜ
乾燥させた木を使う必要があるのかというと
・家の骨組みに乾燥させていない木を使うと栓や
ボルトなどで柱と梁を固定していても木が痩せて
隙間が空いて骨組みがゆるゆるになる
・隙間なくフローリングを貼っていても、木が
痩せて継ぎ目に大きくスキマがあく
こういう現象が起こります。なので一般的には
含水率20%以下の物が普及しています。その
普及している材木はどのような方法で乾燥されて
いるかというと9割はKD材と言われる人工的に
乾燥されている材料になります。自然に乾かした
木材はAD材と呼ばれています。
人工乾燥には高温乾燥と言われる100℃-130℃迄
室温を上昇させて木材の細胞を破壊させて水分を
抜く方法と45度前後の室温で低温除湿乾燥という
方法とバイオ乾燥という室温35度前後で乾燥させ
る方法などがあります。乾燥の精度に関しては
高温乾燥が良く、1週間ほどできちんと含水率を
下げることができますが、低温乾燥は1-2週間で
乾燥できるとは言いますが、含水率にばらつきが
あり完全に乾燥しているとは言い難いのを経験し
ています。低温乾燥でも3か月~半年は期間が
必要だと思います。人工乾燥でも高温で乾燥
させると早く手に入るうえに歪みや割れが少なく
痩せないので隙間ができにくいというメリットが
あります。但し、木の油が抜けて木の強度が無く
なったり、木肌の色が失われたりしてくすんだ
木になります。建築の構造計算では木の強度が
出ないですが、大工の経験上あきらかに違う
んです。その反面、低温で乾燥させたものは
まだ自然乾燥に近く、木の油分もあり木肌も
くすむことはありませんが歪みや割れが発生
しやすいデメリットがあります。
人工乾燥とは別に冒頭でも書きましたが強制的に
乾燥させない自然乾燥があります。自然乾燥の
場合は乾燥して使えるまでに早くても3年の
期間が必要になります。良材になるとはいえ
現実的に考えると常に木を乾燥させるサイクルを
つくならいと中々難しい方法になります。
結論:木は乾燥のさせ方で死んでしまいます。
出来れば低温乾燥やAD材を使うのが理想!!
KD材でも雨や水に濡れなければ100年持ちます。
但し、地震などの大きな力が加わると折れて
しまう。そこを分かったうえで選びましょう。
木を乾かすのが本来の材木屋さんの仕事でした。
今はどこの材木屋さんを見ても運ぶのが仕事に
なっているんじゃないでしょうか。
最近、高温の煙で木を乾かす材木屋さんと出会い
ました。試しに何回か使いました。KD材並みに
乾燥しているのに木が死んでいないし、油分も
残っていてしなりのある木材なんです。どれが
良い悪いとは言いませんがそれぞれのメリット
デメリットをしっかり把握した上で選んで頂き
たいですし、それをきちんと説明して提案して
くれる建築会社に相談したいものですね。
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに
アドバイスをもらいながら進めて
後悔しない家づくりを実現して下さい。
この情報が皆様の役に立てば幸いです。
次回は
【外壁ができるまで1階の床下地をしない理由】
について書きたいと思います。
長い文章を最後まで読んで頂き
ありがとうございました。
今年も残り105日。頑張っていきましょう。
YouTubeでも様々な情報を配信もしていますので
そちらも機会があればご覧ください。
手刻みで建てる木組みの家
株式会社能見工務店
能見太郎
能見工務店の自己紹介!
私たちの家づくりを支える「人」と「想い」をご紹介します。